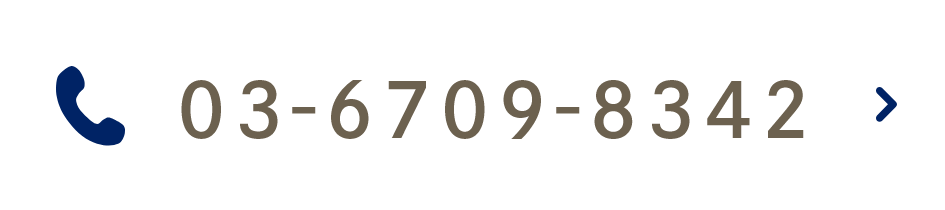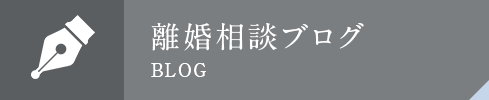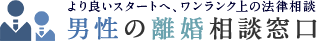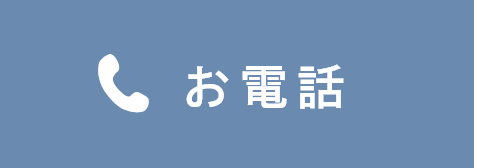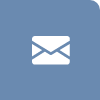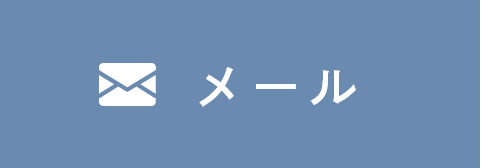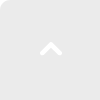養育費の終期はなぜ20歳?
2022.06.14更新
今年4月1日、改正民法が施行され、成人年齢は20歳から18歳に引き下げられました。
成人年齢引き下げに伴い、養育費の終期(いつまで支払うか)も引き下げになるのでしょうか。
成人年齢が変更になれば、養育費の終期も変更になるのが論理的に当然にも思えます。
しかし、裁判所の見解は違います。
裁判所は、改正民法施行の前から、「成人年齢が引き下げになっても、養育費の終期は変わらない」という見解を示してきました。
養育費は、子が未成熟であるから支払われるものである。
成人年齢が引き下げになっても、実態として子が未成熟であることは変わらない。
具体的には、原則的には20歳までとするのが適当である。
大雑把にいえば、以上が裁判所の公式見解です。
しかし、これはおかしいです。
前提として、養育費は、負担者にとっては非常に重い義務です。
一回でも支払いを遅滞すれば、最大で給料の半額まで差押えを受ける可能性があります。
一回差押えを受けてしまえば、受け取る側が取り下げてくれない限り、その後何年も差押えされたままです。
重大な財産権の侵害ですから、厳格な法的正当性が求められるはずです。
民法の条文上、養育費は「子の監護に要する費用の分担」(766条1項)です。
親の子に対する監護権は、親権の一部です(820条)。
子が親の親権に服するのは、成年に達するまでです(818条1項)。
成人したら、子はもはや親権には服しません。
当然、親権の一部である監護権にも服しません。
子が監護権に服さないのに、「子の監護に要する費用」の支払義務が発生するのでしょうか。
18歳を過ぎても親が経済的に生活の面倒を見ている家庭が多い。
これは事実です。
しかし、それは親の義務ではない。あくまで任意です。
だから、経済的に面倒を見ている家庭もあれば、見ていない家庭もあるのです。
実体として子が未成熟であることは、養育費という重い法的義務の発生を正当化しないはずです。
成人年齢が18歳になった以上、養育費支払義務も原則18歳まで。
18歳を過ぎても支払うのは、あくまで当事者の合意がある場合に限る。
これが原則のはずです。
法律に基づき判断すべき裁判所が、「子が未成熟だから」というような曖昧な根拠を持ち出すべきではありません。
18歳を過ぎ成人したら、親と子はもはや成人同士です。
その後の生活費や学費等の負担は、成人同士、当事者同士で合意するのが原則のはずです。
裁判所の見解は理屈が通っておらず、説得力にも乏しいです。
成人年齢が引き下げになった以上、養育費の終期も原則として引き下げられるべきです。