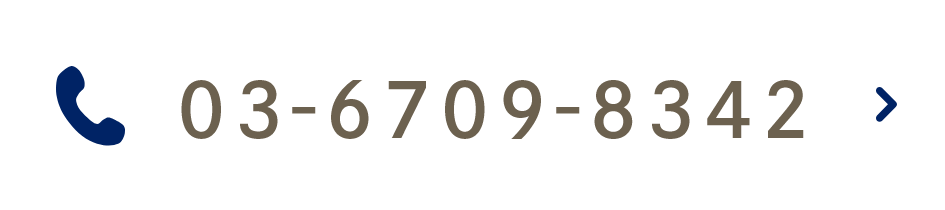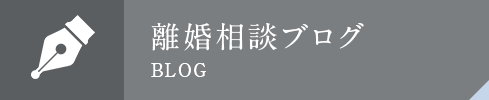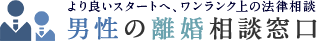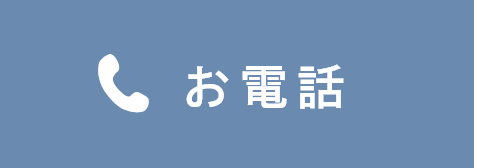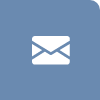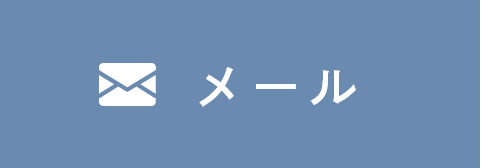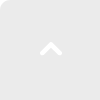財産分与は必ず2分の1ずつでなければいけないのか
2019.04.18更新
アマゾン創業者ジェフ・ベゾス氏の元妻マッケンジー氏は、離婚に伴う財産分与でおよそ4兆円を得たと報じられました。
離婚が報じられた際には、ベゾス氏の財産の2分の1であるおよそ7兆円を得るのではないかと言われていました。
巨額には変わりませんが、だいぶ予想よりは少なかったことになります。
7兆円という予想の根拠は、元夫妻の暮らすワシントン州法では
「夫婦の共有財産は2分の1に分けなければいけない」
と明文で定められているからです。
それよりも少なくなった事情は外には伝わってきていません。
日本でも、財産分与は2分の1ずつという例がほとんどです。
しかし、日本の法律を見ると、ワシントン州法とは異なり、「2分の1」とは明記されていません。
民法768条(財産分与)によれば、
「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。」
としているだけです。
裁判所に持ち込まれた場合については、
「家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。」
とされています。
要は、事情に応じて分け方は変わってくるよ、ということです。
それがなぜ「原則2分の1」となっているのか。
その背景には、恐らく、「夫は外で働き、妻は家庭を守る」という旧来の役割分担意識があります。
妻の内助の功あってこそ、夫は外で働き、金を稼いだ。
だから、離婚にあたっては半分ずつに分けるべきだ、というわけです。
でも、この考え方は現在でも妥当でしょうか。
夫婦の役割分担は夫婦それぞれです。
2分の1を当然の前提としなくても、もっと柔軟な解決があって良いはずです。
せっかく民法が、柔軟な解決を認める書き方をしているのです。
活かさない手はありません。
ところで、ワシントン州に限らず、アメリカ各州の法律を見ると、どこも「財産と負債を2分の1に分ける」と定めていることに気づきます。
日本では、住宅ローンを除き、借金は分与の対象にならないのが原則です。
裁判所も弁護士も、それを当然として受け入れています。
でも、国が変われば当然のように借金も2分の1に分けることが原則になっていたりする。
これは発見でした。