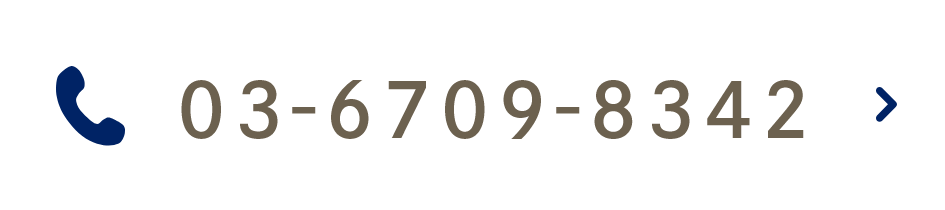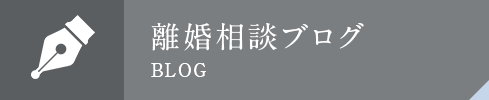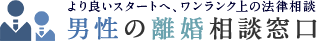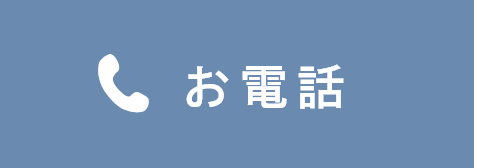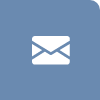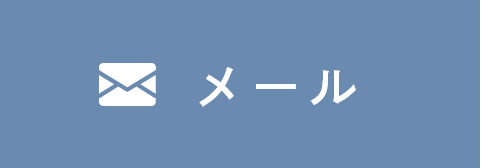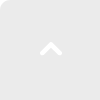離婚事件とメンタルヘルス
2022.06.23更新
離婚事件を一定数以上扱っている弁護士なら、恐らく誰でも気づくことがあります。
「離婚事件」と「メンタルヘルス」の密接な関係性です。
離婚事件は、当事者のいずれかにメンタルヘルスの問題がある件の割合が非常に高いのです。
離婚紛争は強いストレスがかかります。
離婚に発展するような結婚生活自体、大きなストレス源でしょう。
しかし、当事者のエピソードを聞く限り、多くの場合、ストレスを生んでいるのはむしろメンタルヘルスの方です。
メンタルヘルスが離婚紛争を生んでいるのです。
素人診断で「メンタルヘルスに問題がある」と言っているのではありません。
通院歴があり、診断名もついていて、服薬もしている。
医学的にも「メンタルヘルスに問題がある」方の割合が有意に高いのです。
それも、「少し」ではなく「驚くほど」高いです。
離婚事件とメンタルヘルスの密接な結びつきを知っておくことは、当事者にとって時に大きな意味があります。
離婚事件では、相手からの理不尽な要求に振り回されがちです。
そんな時、相手の要求の裏に「何らかの目的があるのではないか」と考えると、時に間違えます。
金目当てなんじゃないか。
家が欲しいんじゃないか。
実家もグルなんじゃないか。
不貞相手がいるんじゃないか。
相手が合理的に行動しているなら、その可能性はあるでしょう。
しかし、メンタルヘルスに問題がある方の場合、単にその問題の表れ、一症状に過ぎない可能性があります。
自身の内的な問題を別の形で訴えているだけで、合理的な目的などはない。
落としどころも考えていない。
そういうケースの場合、私はまず相談者の方に
「相手の行動を合理的に解釈するのを止めましょう。」
と伝えることにしています。
そういうケースの全体に占める割合は、恐らく想像よりずっと大きいです。