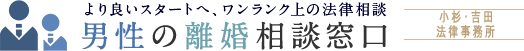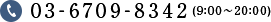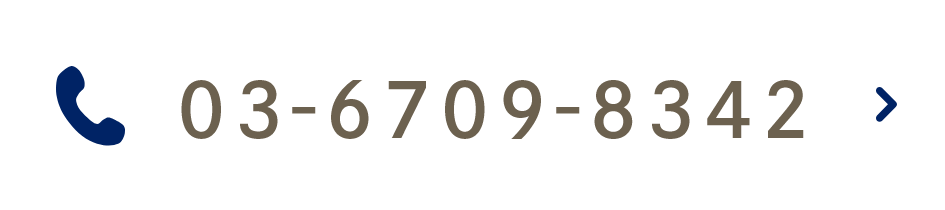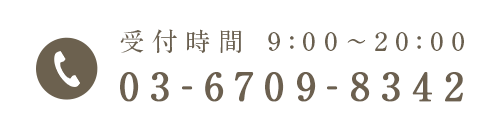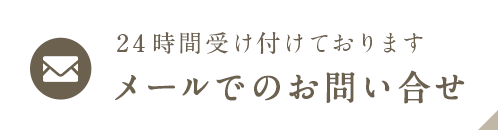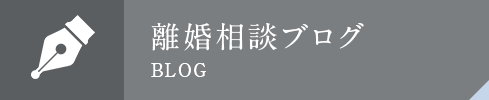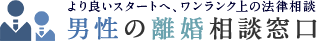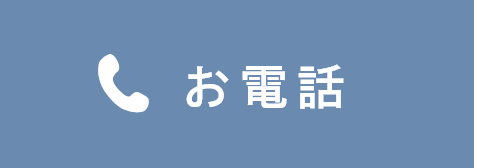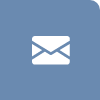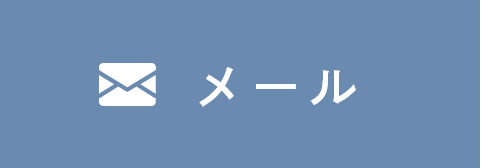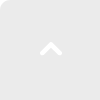離婚届に保証人が必要なのは憲法24条違反では?
2019.02.26更新
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」
憲法第24条はそう定めています。
ところで、協議離婚の際に自治体に提出する離婚届には、保証人として2名の成人の署名押印が必要です。
一体なんで離婚に保証人が必要なのでしょうか?
私は、協議離婚に保証人が必要とされるのは、憲法第24条に違反しているのではないか、と考えています。
まず、「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」するというのは、親などの第三者から命じられての婚姻を禁じる趣旨です。
要は、「家」制度の否定です。
この点は争いはありません。
次に、「婚姻が両性の合意のみに基づいて成立」するなら、離婚も両性の合意のみに基づいて成立しなければおかしいです。
婚姻が両性の合意のみに基づいて成立している以上、両性が合意の上で婚姻解消を望むなら、婚姻は解消されないといけません。
ところが、離婚届の書式は、離婚の成立に保証人2名を求めています。
保証人を見つけることができなければ、両性が合意の上離婚を望んでいても、離婚できないのです。
これは、離婚に保証人たる2名の同意を要件と課すのと同じです。
両性の合意のみによって成立すべき離婚に、第三者の同意を条件としているのです。
一般の保証人と同様、ここで保証人として第一に想定されているのはおそらく「両親」です。
両家の家長たる父が保証人として名を連ねて、はじめて離婚できる。
離婚届の書式がイメージしているのは、そんな離婚ではないでしょうか。
これが憲法24条違反でなくてなんでしょう。
婚姻は両性の合意のみによって成立するが、いったん成立した婚姻を解消する際には、関係者の同意を必要とする。
それも1つの意見です。
でもそれは、現在の協議離婚を支えるところの「離婚は個人の自由である」という考え方と矛盾します。
要は、離婚届一枚で成立する「協議離婚」なるものは、個人の自由の尊重などとはな何の関係もない、「家」制度に根ざすものだということ。
その証が、離婚に際して求められる「保証人」なのだと思います。
私は、現在の「離婚届1枚で成立する離婚」という制度が守られるべきだとは考えません。
しかし、仮にそのような制度が維持されることが前提なら、保証人が求められることは明確に違憲である。
そう考えています。
弁護士 小杉 俊介