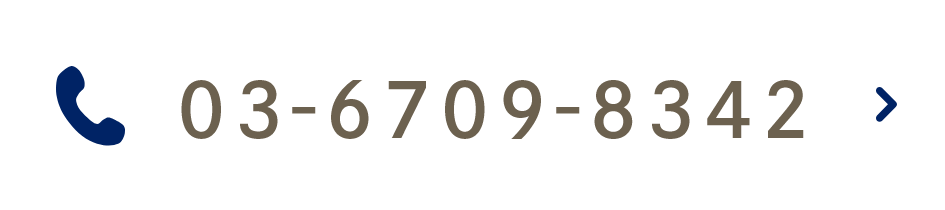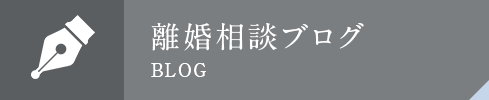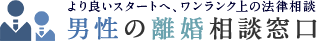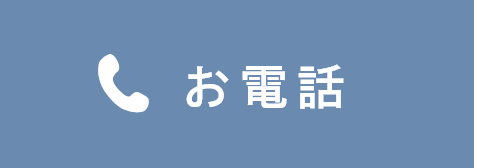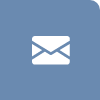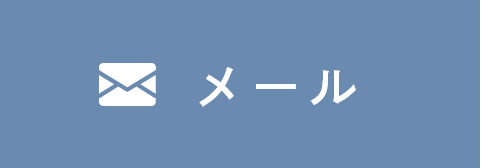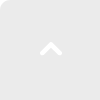子のいる離婚は「連れ去り勝ち」とよく言われます。
先に子を連れて家を出てしまえば、別居の理由を問わず婚姻費用を請求できる。
婚姻費用は算定表に基づきほぼ自動的に決まるし、給料の差し押さえもできる。
婚姻費用の負担は重いので、離婚を渋る相手を兵糧攻めで離婚に追い込める。
面会交流を実施するかは、自分の気持ちで決められる。
新住所を隠そうと思えば役所だって裁判所だって協力してくれる。
そして、現に子を監護していることが重視されて、子の親権も獲得できる。
この一連の流れを「連れ去り勝ち」と呼ぶなら、確かに現在の離婚は「連れ去り勝ち」です。
個人的には、上記のような行動が「正解」になってしまうのは制度の欠陥だと考えています。
弁護士が制度の穴をつくような手段を教唆するのも良くないと思います。
しかし、「制度の欠陥だ」と言っているだけでは相談者/依頼者の方には何の役にも立ちません。
では、どのような対抗手段が考えられるでしょうか。
現行の制度上、子を連れて別居されてしまった後に出来ることは限られています。
経験上、最も有効な対抗手段は、単純ですが「先に介入すること」です。
配偶者が子を連れて出ていこうとしている気配があったら、先に弁護士から受任通知を送ってしまう。
受任通知中に、
「子の福祉に配慮し、くれぐれも子の現状を動かさないこと。
万一、協議なく子を連れて出た場合には警察に通報する。」
旨を記載する。
可能であれば、ほぼ同時に離婚調停も申し立ててしまう。
要は、連れ去る側と同様の行動を先にしてしまうことです。
正直に言えば、弁護士の受任通知程度では法的強制力はありません。
相手が連れ去ろうと思えば、受任通知が届いていようがいまいが連れ去りは可能です。
しかし、実際には先に受任通知が届いてしまえば、連れ去りを躊躇する相手が多数派というのが実感です。
理由としては、連れ去る側も自身の行為が100%正しいとは思っていないので、先に釘を刺されると慎重にならざるを得ない、という心理的な側面があると思います。
また、理屈で言っても、婚姻中は父母は共同で親権を行使するのが原則です。
片方に断りなく子の居所を移すことが正当化されるのはかなり緊急性の高い場合に限られるはずです。
具体的には、離婚意思は固いが、夫婦間の権力関係等の問題で話し合いが成立しないので、先に別居するしかない。
子を主に監護しているのは自分なので、別居の際には連れていくしかない。
子を連れて別居すると言ったら反対されるに決まってるので、気付かれる前に強硬するしかない。
そういった場面に限られるはずです。
しかし、当事者間では話し合いは成立しなくとも、第三者である弁護士が相手であれば協議は可能なはずです。
つまり、先に弁護士に委任してしまえば、「話し合いが成立しない」という言い訳が通用しなくなるのです。
以上のような理由で、とにかく先に介入してしまうことで「連れ去り勝ち」に一定程度対抗することができます。
この手段には誰でも気づく大きな欠点があります。
連れ去られる前に気付かないと意味がない、ということです。
この対抗手段があることを知っている相手であれば、なおのこと隠密に進めるはずです。
本当に前触れなくいきなり連れ去られた場合にはこの手段は取れません。
しかし、私が見聞する範囲では、多くの場合、何らかの前触れがあります。
その前触れを見逃さず、まずは相談に来ていただきたい。
どんなに早くても相談後にしか介入できない弁護士の立場では、そう願うことしかできません。
でも、いったん先に動くことができれば、「連れ去り勝ち」に対抗することは十分可能です。
「連れ去り勝ち」の現状は間違っています。
いつまでもこの間違った状態が続くとも思いません。
しかし、「連れ去り勝ち」が否定できないうちは、上記のような方法をはじめ手段を尽くして対抗するしかありません。