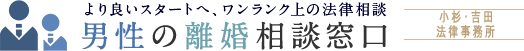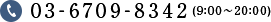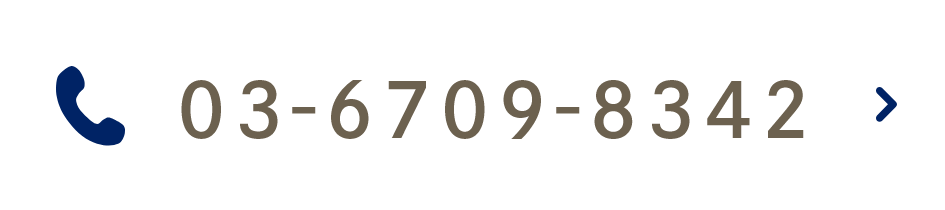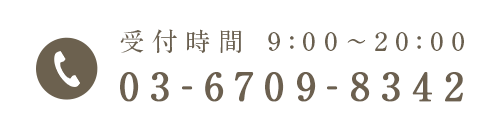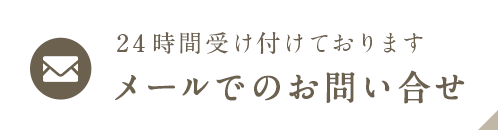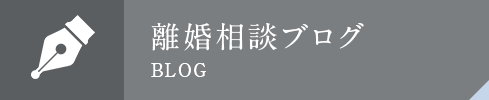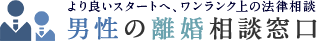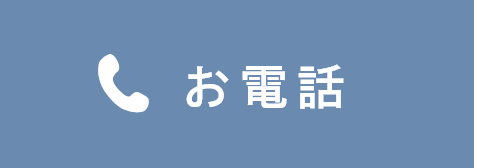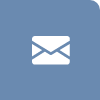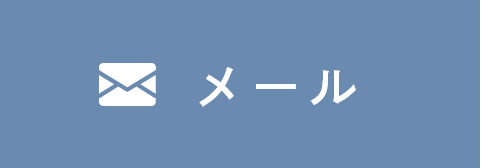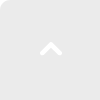amazon経営者のジェフ・ベゾス氏が離婚するとのこと。
個人的に何を知っているわけでもありません。
ただ、世界一の富豪だけに、経営者の離婚についての分かりやすい説明例になりそうです。
まず、創業者の場合、資産の多くは会社の持分(株式)です。
資産なので、当然、財産分与の対象になります。
でも、これから他人になる人に会社の一部を分け与えるのは現実的ではありません。
他の利害関係者も反対するでしょう。
代わりに現金で分与を行おうとしても、そんな現金はありません。
ベソス氏の場合、7兆円を超えるなんて話もあります。
そんな現金を作ろうと思ったら、それこそ株式を売却するしかありません。
もちろん、それも現実的ではありません。
日本ではまだ例は多くないですが、海外では婚前契約で対処していることも多いと聞きます。
ただ、ベソス氏の場合、結婚が25年前、まだamazon創業前とのこと。
会社がここまで大きくなることを見越して契約している可能性は高くなさそうです。
こうやってニュースになっているからには、当事者間で合意ができているということでしょう。
でも、合意できない場合、経営者の離婚は相当難しい、ということが実感できます。
もう1つ。
こういうニュースに触れたり、実際に経営者の方からの相談を受けたりする際につくづく感じるのは、経済的成功と夫婦関係の円満の複雑な関係です。
普通は、経済面での失敗は夫婦不和の原因です。
ありていに言えば、夫の稼ぎが少ないと、夫婦関係は上手くいかない。
弁護士として相談を受けていても、実際にそういう傾向は明らかです。
それを逆に考えれば、稼ぎが多ければ夫婦関係は円満に行きそうです。
会社員ならあり得ないような収入を得る会社経営者ならなおさらです。
ところが、現実には、会社の成功とともに夫婦関係が上手く行かなくなった、という例をよく聞きます。
経済的成功はむしろ夫婦不和の方向に働く要素なのではないか、と思わされるほどです。
自由になる金が増えたことによって私生活で問題が発生する、という面ももちろんあります。
でも、それだけではなさそう、というのが私の実感です。
明確な答えを持っているわけではありません。
ただ、夫婦というのは微妙なバランスの上に成り立っているものだ、ということは言えそうです。
弁護士 小杉 俊介