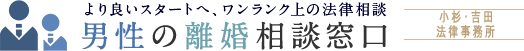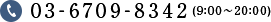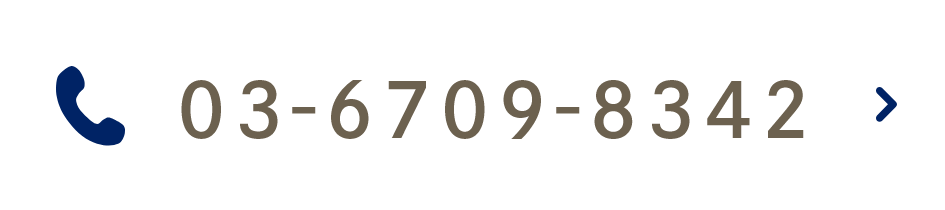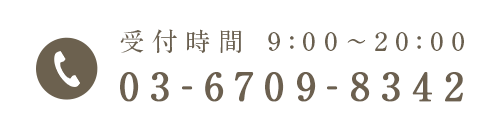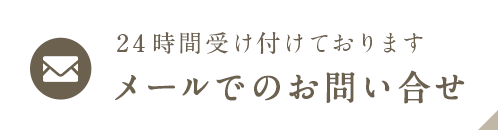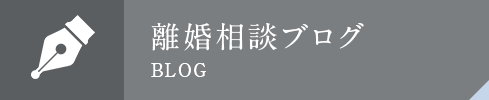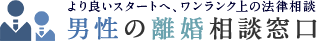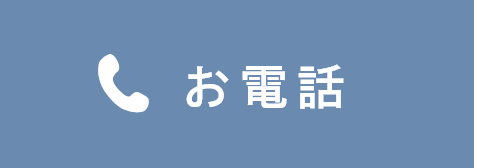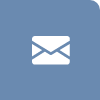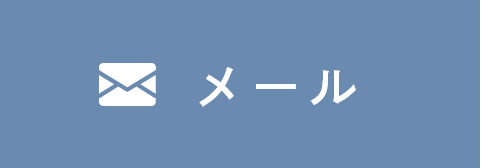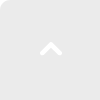選択的夫婦別姓制度の実現を求める声は大きいです。
「共同親権」については反対の声が大きい弁護士業界ですが、「夫婦別姓」については賛成が多数という印象です。
私は「夫婦別姓」についてはこれまで消極的反対でした。
しかし、最近になって、積極的とまでは行きませんが、消極的賛成に転じました。
理由は、「夫婦別姓」と「共同親権」は実は根本は共通しているのではないか、と考えるようになったからです。
「夫婦別姓」については、保守の立場から、「家族の絆を弱める」という批判が強い、と言われています。
実は、私も大雑把に言えばその観点から反対でした。
都市に住む「意識の高い」人たちは別にいいんです。
夫婦別姓だろうと同姓だろうと、きちんと子に対する責任を意識し、家庭を営んでいくでしょう。
でも、世の中はそういう人たちばかりではありません。
「姓を同じくする家族になる」という形式が整って始めて家族に対する責任を意識する。
そういう人たちが少数派だとは、私には思えません。
そういう人たちにとって、選択的であっても夫婦別姓となれば、「夫婦なんて結婚してもしょせんは他人」という意識にお墨付きを与えることにならないでしょうか。
夫婦が他人なのは別にいいとして、問題は、姓を異にする子についても「しょせんは他人」という意識につならがらないか、という点です。
家族全員が姓をそろえて、初めて「自分は新しく家族を作ったんだ、だから配偶者にも子にも責任を負うんだ」と実感する。
良い悪いではなく、夫婦同姓という制度には、家族としての自覚を促す機能があります。
夫婦別姓推進派の議論には、夫婦同姓という制度が実際に持つそういった機能が失われかねないことへの視点が欠けている。
それが、夫婦別姓に消極的に反対する理由でした。
しかし、考えてみれば、姓を同じくして初めて子に対する責任を実感するという意識の背景にあるのは、「イエ」制度に他なりません。
家長たるもの、家の構成員には責任を持つ、というわけです。
しかし、そもそも、親と子の結びつきには「イエ」は必ずしも必要ではありません。
親たるもの子に対して責任を持つ、それで十分なはずです。
しかし、ここで問題になるのが「離婚後単独親権」です。
どう擁護しようが、離婚後単独親権は「イエ」制度を土台とする仕組みです。
「イエ」制度を土台とする限り、離婚後には子はどちらかの「イエ」に属することになる。
離婚の時点で、共通の「イエ」を持たない親と子の関係は切り離されてしまうのです。
しかし、「離婚後共同親権」ならどうでしょう。
その場合、離婚自体は親と子の関係に影響を与えません。
親と子の関係を「イエ」が媒介しないからです。
離婚しようがしまいが、子ができた以上、親として子に責任を持つ。
そのことが制度上明確になれば、夫婦が結婚時に「姓をそろえる」という儀式を経なくても、親としての自覚は自然に生まれるのではないでしょうか。
そうなれば、もはや夫婦同姓を強制する必然性はなくなります。
「夫婦別姓」と「共同親権」の根っこが同じというのは、そういう意味です。
どちらも問題は「イエ」制度であり、その具体化として戸籍制度なのです。
以上の次第で、私は、共同親権の実現と同時であれば、夫婦別姓も実現されるべき、という立場をとるようになりました。
1つだけ最後に。
夫婦別姓論者から、「選択的夫婦別姓になったって、あんたは困らないのになぜ反対するのか。」という意見をよく聞きます。
このような意見は、国という共同体の基礎となる家族という制度の重要性を理解していないのではないでしょうか。
しかも、反対論者のことを自分たちより知的に劣位であるとみなしているという点で失礼です。
もっと建設的な議論を望みます。