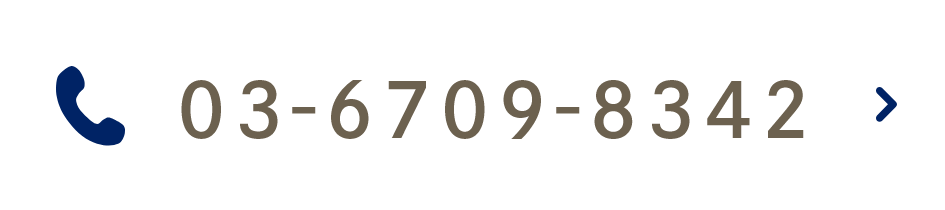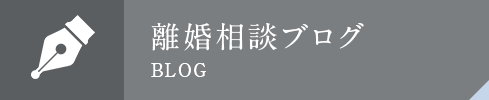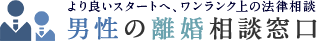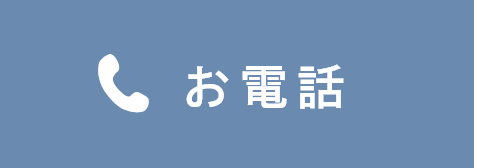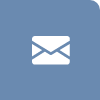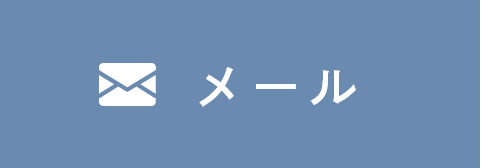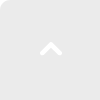海外赴任中に離婚するとき困ること
2018.12.29更新
海外赴任中に、日本に残した配偶者と離婚したい。
でも、離婚に同意してくれないので、調停を申し立てたい。
そんなとき問題となるが、裁判所です。
離婚調停は、原則として、相手方の住所を管轄する家庭裁判所に申し立てないといけません。
要は、日本の裁判所に申し立てる必要があります。
調停が始まれば、およそ1月に一度、期日が入ります。
自分で調停を起こした場合、本人が出席しないといけませんので、1月に1度帰国しないといけません。
それは現実的ではないでしょう。
弁護士を代理人に立てた場合でも、原則として、第1回と、離婚がまとまる回は出席する必要があります。
ただ、それ以外の期日は代理人のみの出席で進めることは可能です。
海外在住の方が当事者の調停は、正直なところ、2人とも国内にいる場合よりも面倒なことが多いです。
調停の回数も増えがちです。
でも、代理人の工夫次第で、国内と同様に進めることも可能ではないかと思っています。
本当の問題は、夫婦2人とも海外にいる場合ですが、それはまた今度。
小杉