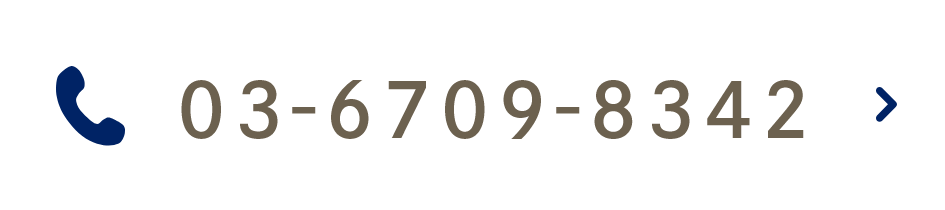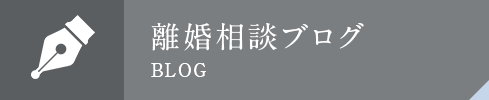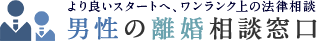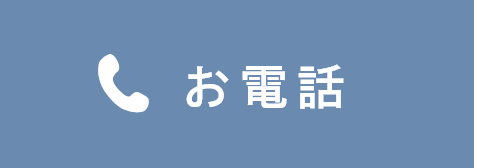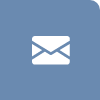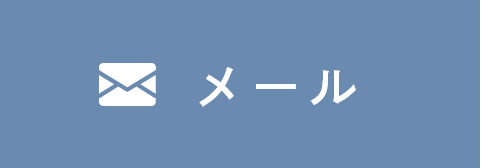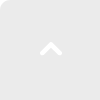『ジュリアン』評についてもう少し
2019.03.05更新
realsound映画部に掲載していただいた映画『ジュリアン』の映画評について、少し補足したいと思います。
後付けの言い訳のように取られるのは本意ではないのですが、この映画についてはもう少し説明しておいた方が良いと考えました。
そもそもこの記事を書き、realsound映画部編集部に掲載していただいたのは、この映画について非常に問題のある取り上げられ方が目についたからです。
以下、もう少し詳しく説明します。
まず、この点はきちっと断っておかなければいけません。
この映画の作品としての評価です。
私は『ジュリアン』は正直なところ「大したことない」映画だと考えています。
これは別に悪口ではないですし、記事で論評した内容とも矛盾しません。
誠実で、論評に値する映画だとは思います。
でも同時に、映画としてはやはり「大したことない」。
脚本の練られ方も、俳優の演技も、演出の冴えも、特出したものはこの映画にはありません。
劇伴を排しリアリズムにこだわった意図はよく理解できますが、工夫の無さが目につきます。
記事中で取り上げた「プラウド・メアリー」の使い方を例に挙げます。
記事では歌詞を例示し、この曲を歌ったアイク&ティナ・ターナーの背景を紹介し、なぜこの曲が使われたのかを分析しました。
記事で述べたのはあくまで私の解釈ですが、この解釈が間違っている可能性はまずないと思います。
自分の解釈力に自信がある、ということでは別にありません。
この曲の使われ方が、他の解釈があり得ないくらい「ベタ」だからです。
はっきり言って、例えば現在のアメリカの映画やドラマで、これほどベタなポップミュージックの使われ方を見ることは滅多にありません。
現代は、配信サービスを通じていつでも海外ドラマの最先端に触れることができる時代です。
アマゾンプライムの「ホームカミング」でも、ネットフリックスの「ロシアン・ドール」でもいいです。
「プラウド・メアリー」をフルコーラス使って家出少女の決意を語るとか、DVのイメージを忍ばせるといったレベルの、説明的で野暮ったいポップミュージックの使い方など一切出てこないのが分かります。
このシーンが分かりやすく象徴するように、はっきり言ってこの映画は作品として決してレベルは高くないです。
しかし、そのことは単体では別に取り上げるほどのことではありません。
問題なのは、これほど明確に、ベタに、野暮ったく「親子関係の二面性」を描いた演出意図を酌んだ論評がまるでなかったことです。
これほど明確な演出を見逃して、映画という作品について何を語るというのでしょうか。
気づいた自分が偉い、と言いたいのではないです。
記事でも書いたとおり、この「プラウド・メアリー」の場面は、物事の多面性を示す、映画の鍵の部分です。
父親は一面的な加害者ではないし、母親と小さい子も一面的な被害者ではない。
人間はそんな単純ではない。
それをこれだけ分かりやすい演出で示されていることをスルーし、あたかもこの映画が父親が加害者であり、母と子が被害者だと描いた映画だということにする紹介が目につきました。
より悪いのは、この映画があたかも「共同親権の悪」を描いた作品であるかのように紹介した方たちです。
私の同業者にも何人もいました。
共同親権の問題点を指摘し、日本独自の離婚後単独親権を擁護する文脈でこの映画を持ち出す論をたくさん見ました。
「大したことない」映画だと書きましたが、さすがにそこまで薄く浅い一面的な映画ではありません。
そもそも映画という芸術はそのような一面的な意見を伝えるものではないです。
そもそもこの映画は共同親権なり単独親権なり、親権の在り方について描いた映画なのでしょうか。
見た方なら分かると思いますが、この映画の問題意識はあくまで「DV」です。
離婚してもなおもDVが続くことについて描いた映画だ、というなら分かります。
しかし、それ以上に離婚後の親権がどうあるべきか、という点はこの映画では特に取り上げられていません。
もしそのような問題意識をこの映画から読み取ったなら、それはこの映画の中にあったものではなく、自分の中にはじめからあった意見を勝手に投影しただけです。
そもそも、離婚後単独親権という制度を維持している国は、いわゆる先進国では日本だけです。
そして、各国はかつての単独親権から共同親権へと移行してきたのであって、逆に共同親権から単独親権へ移行した例など聞いたことがありません。
当たり前です。
父権性を前提として、子を親の所有物として扱う単独親権から、子を独立した個人として扱い、父母を平等に扱う共同親権へ。
個人の自由と民主主義を前提とする限り、この流れに異を唱える意見など出てきようがありません。
断言しても良いですが、『ジュリアン』の監督に共同親権に異議を唱える意識などありません。
そもそも、共同親権以外の選択肢がある、ということ自体、日本以外の国の人は意識していないはずです。
ここ日本で、共同親権を問題視し、強制的単独親権を支持する根拠としてこの映画が持ち出されているなんて、多くのフランスの方にとってきっと想像外なんじゃないでしょうか。
なのに、なぜ『ジュリアン』が「共同親権の闇を暴いた映画」として紹介されてしまったのか。
この答えが恐らく正しいのではないか、という仮説があります。
それは、『ジュリアン』がアメリカでは『CUSTODY』=「親権」というタイトルをつけられているから、です。
恐らく理由はそれだけです。
なぜ「親権」というタイトルになったか。
これは推測ですが、「プラウド・メアリー」を軸として「親権」なる制度の両面性を描いた作品である、と担当者が考えたからではないでしょうか。
『CUSTODY』というそっけないタイトルには、「親権」についての意見は何ら含まれていません。ニュートラルです。
なるほど、この映画を構成する2つのプロット=ジュリアンとジョゼフィーヌのストーリーに共通するのは、「親権」だな。
じゃあ『親権』でいこう。
そんな感じでつけられた英語タイトルに思えます。
ところが、この映画が日本に紹介されるにあたり、『CUSTODY』という英語タイトルも一緒についてきた。
そうか、この映画のテーマは「親権」か。
とすると、作中で描かれるDVも「親権」に由来するのか。
ところでフランスは共同親権だ、とするとこの映画の描く悲劇も共同親権から生まれるのか!
その程度の単純な発想じゃないでしょうか。
『ジュリアン』に限らず、外国映画、特にアメリカ以外の国の映画が日本に紹介される際には、その紹介のされ方が映画の解釈にまで過剰に影響を持ってしまう、という例はよく見ます。
その映画の作られた文脈も、言語も100%は共有していない以上、それはある程度仕方がないことです。
しかし、『ジュリアン』についてはその弊害がかなり目につきました。
自分の主張につなげるため、人様が作った映画の趣旨まで捻じ曲げる。
それはやってはいけないことです。
少なくとも、この映画を「共同親権の問題点を描いた映画」だとして紹介した人は、自分の主張のためには嘘をつくことも何とも思わないほど不誠実か、映画をはじめアートというものがそもそもまったく分からないか、あるいはその両方です。
この解釈が間違っている可能性もほぼないと思います。